
東洋医学・
漢方薬治療

当院の東洋医学について
東洋医学と西洋医学、両方の視点に立って医療を届ける
おひさまでは頭痛やめまいの患者さんを中心に東洋医学的な診療も行っております。
脳の病気をご心配されて脳神経外科クリニックである当院を受診される方がほとんどですので、まずは神経症状の診察と、必要やご希望に応じてMRI・CTの頭部画像検査を行い、脳卒中や脳腫瘍などの大きな病気ではないことを確認いたします。
西洋医学的な診察で診断がつく場合は、西洋薬による治療を進めていきます。
一方、西洋医学的には診断がつかない方も多くおられ、そのような場合には東洋医学に基づいた診察もさせていただき、保険診療で漢方薬のエキス剤処方を提案させていただいております。
東洋医学を取り入れたきっかけ
関連病院勤務医時代や、大学病院からの派遣先病院で非常勤の外来担当をさせていただく時に、頭痛・めまいの患者さんの診療をする機会がたくさんありました。
西洋医学的なアプローチしかできないため、診察と画像診断で危険な病気を否定した後は、西洋薬の痛み止め・めまい薬を処方する選択肢しか持っていませんでした。
しかし、こうした治療だけでは患者さんの症状や悩みが解決できないことも多く、物足りなさを感じておりました。
当院では、西洋医学と東洋医学、両方の良いところを取り入れ、広い選択肢の中から患者さまに最適な医療を選んでいただくことができるようサポートして参ります。
東洋医学による治療とお薬
高血圧症の治療
例えば、脳卒中の原因にもなる高血圧症の場合、血圧をしっかりと下げることは漢方薬ではなかなか難しく、効力は西洋薬が強いです。脳梗塞予防の抗血小板薬・抗凝固薬、いわゆる「血液サラサラのお薬」も西洋薬が優先となります。
頭痛の治療
頭痛の診療でも同様に、「片頭痛」であれば西洋薬による治療をまずは優先します。
しかし、頭痛で来られる患者さんの中には国際頭痛分類による「片頭痛」の診断基準には当てはまらない方もたくさんおられます。こうした患者さんの頭痛の原因を探っていきますと、肩こり・ストレス・体の冷えなどが隠れていることがあります。「冷え」の概念は西洋医学にはなく、その治療も東洋医学・漢方薬治療ならではのものになります。
「頭痛の診療ガイドライン2021」でも、「漢方薬は伝統医学をもとに、経験的に使用されてきた治療薬である。頭痛に対しても各種の漢方薬が経験的に使用され、効果を示している。近年では徐々に科学的エビデンスも集積されつつあり、頭痛治療に対する有効性を裏づけている。(弱い推奨/エビデンスの確実性B)」とされています。
代表的な漢方薬
- 葛根湯(かっこんとう)
- 五苓散(ごれいさん)
- 呉茱萸湯(ごしゅゆとう)
- 桂枝人参湯(けいしにんじんとう)
- 釣藤散(ちょうとうさん)
めまいの治療
めまいの患者さんも、耳鼻咽喉科の先生方の領域である内耳障害のめまいや、脳の病気では小脳の脳卒中などが有名です。
しかし、実際の患者さんの多くはそのどちらでもなく、季節の変わり目やストレスによる自律神経の不調などが原因のことが多いです。
こうした体の不調のサインとして出てくる「めまい」の原因を探り、そこへアプローチして治療するのも東洋医学的な診療に手ごたえを感じています。
代表的な漢方薬
- 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
- 五苓散(ごれいさん)
- 真武湯(しんぶとう)
- 半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)
診察時のご案内
腹診(ふくしん)・舌診(ぜつしん)・脈診(みゃくしん)
脳神経外科のクリニックですが、東洋医学の診察をする場合は、お腹を診させていただくことがあります。「頭痛で脳外科に来ているのに、お腹まで出すんですか?」と、不思議がる患者さんもいらっしゃいますが、腹診は東洋医学では重要な診察項目なのです。腹の筋肉の張り具合、押して痛いところや違和感がないかなどを診察していきます。
例えば、上腹部で肋骨の下側の淵を圧迫したときに痛みや抵抗感があれば、これはストレスの強い状態を示しており、ストレスを和らげる生薬が入った漢方薬を選ぶ基準にすることがあります。
東洋医学的な診察では舌の状態を診る「舌診(ぜつしん)」、脈の強さなどを詳しく診る「脈診(みゃくしん)」も大切です。これらを組み合わせて全身の「気(き)」・「血(けつ)」・「水(すい)」の状態を判断し、漢方薬の処方を選びます。
令和6年5月8日から水曜日午前中に漢方専門外来が始まります!
令和6年5月の連休明けから、広島大学病院の漢方診療センターの専門医の先生に週1回当院へ非常勤でお越しいただきます。
頭痛・めまいの他にも、食欲がでない・疲れやすい・冷え症・眠れない・腰が痛いなどのお悩みや、西洋医学的な治療では治りにくかった症状はなんでも相談可能です。
また、当院の特徴である歯科との連携の観点から、口が乾く・味覚障害などの症状も診療が可能です。
河原 章浩 先生
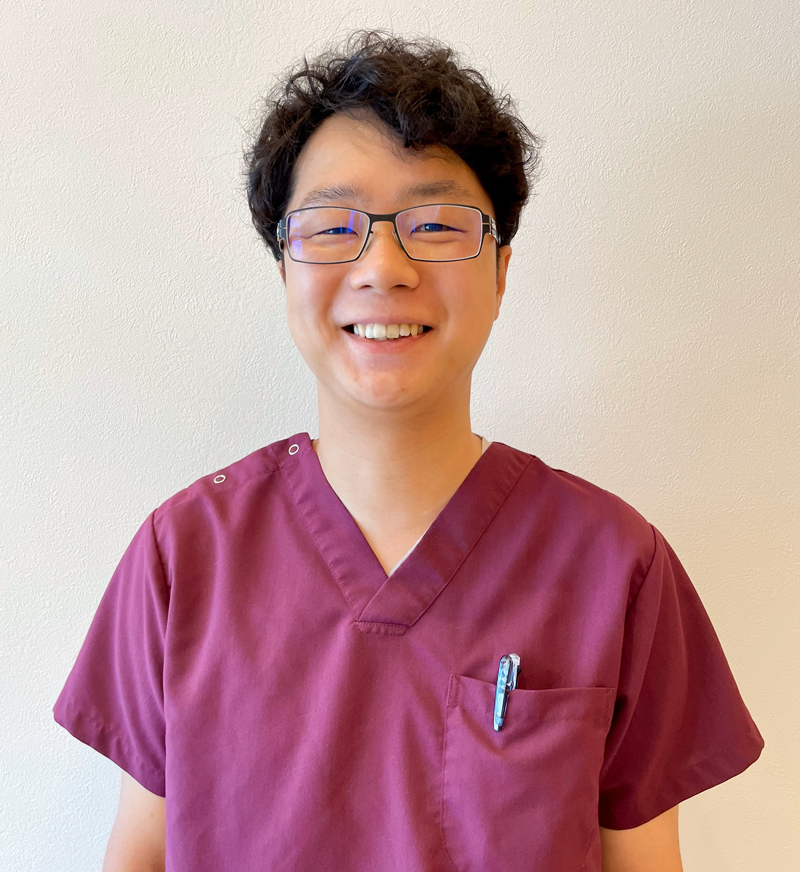
広島大学病院 漢方診療センター 助教
平成24年 埼玉医科大学医学部卒業
日本東洋医学会 専門医
日本内科学会 認定医
日本プライマリ・ケア連合学会 家庭医療 指導医・専門医
日本病院総合診療医学会 認定医
日本専門医機構 総合診療専門研修特任指導医