
おひさまノート
睡眠時に急に息が吸えなくなるのはなぜ?考えられる原因や対策、受診先の選び方を解説
目次
「睡眠中に息が吸えなくなって目が覚めた」――そんな経験の背景には、見過ごせない深刻な病気が隠れていることがあります。
この記事では、睡眠中に息が吸えなくなる原因や注意すべき症状、受診先の選び方について解説します。
息苦しさを和らげるセルフケアも紹介していますが、症状が続く場合や強い息苦しさを感じる場合は、早めに医療機関を受診してください。
睡眠中に息が苦しくて目が覚める場合に考えられる原因

睡眠中に急に息が吸えなくなることは珍しくありませんが、背後には放置できない疾患が隠れている場合があります。
主な原因として、以下の4つが挙げられます。
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 呼吸器(肺や気管・気管支)の病気
- 心臓や血管の病気
- ストレスや精神的要素
それぞれの症状や注意点を順に解説していきます。
夜間発症の息苦しさを放置すると、重症化することや命に関わるリスクが高まることもあります。軽視せず、医療機関の受診を検討しましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に10秒以上の呼吸停止や低呼吸が繰り返される疾患です(※1)。
睡眠中の呼吸困難以外に以下の症状がある場合、睡眠時無呼吸症候群が疑われます。
- 大きないびき(家族から指摘されることが多い)
- 日中の強い眠気や倦怠感
- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)
- 朝の頭痛や熟睡感のなさ
- 夜間頻尿
- 起床時の口の渇き
- 集中力低下や仕事・勉強のパフォーマンス低下
睡眠時に低酸素状態が続くと、脳や血管に負担がかかり、高血圧、心不全、脳卒中など重大な合併症リスクが高まります。
慢性的ないびきや呼吸停止、日中の眠気などの典型症状があれば、速やかに医療機関の受診が推奨されます。
(※1 参考)日本呼吸器学会|睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020
呼吸器の病気

喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、気道の慢性的な炎症や狭窄により、息苦しさ、咳、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー音)が出やすくなります(※1)。
いずれも夜間や早朝に症状が悪化しやすく、自律神経やホルモン分泌の日内変動が要因とされています。
一方、肺炎や気胸は急性発症型で、突然の呼吸困難や胸痛、発熱などが急激に増悪する恐れがあり、迅速な医療介入が必要です(※2)。
夜間や早朝の息苦しさに加え、咳や胸痛などの症状が見られる場合は、自己判断せず速やかに呼吸器内科での検査を受けることが推奨されます。
(※1 参考)日本呼吸器学会|COPD診断と治療のためのガイドライン第6版 2022
(※2 参考)日本呼吸器学会|急性呼吸不全・ARDS
心臓や血管の病気

心不全や不整脈などの心血管疾患では、夜間の呼吸困難、動悸、胸の圧迫感、下肢むくみが現れることがあります。
起きて生活している時間には下の位置にあった下半身は、夜間睡眠中は心臓と同じ高さになります。
そうすると、下半身からの血液が心臓に戻ってきやすくなります。
健全な方はその変化に問題なく対応できますが、心臓のポンプ機能が低下している場合、肺に血液が滞留する「肺うっ血」が生じることがあります。
肺うっ血は呼吸困難や胸の圧迫感を誘発します。
夜間の呼吸症状に加え、倦怠感やむくみを伴う場合は、心不全の進行を示す重要なサインの一つです(※1)。
高齢者や糖尿病、高血圧などの循環器疾患リスクのある方は症状が進行しやすいため、息苦しさやむくみを自覚した際は、早めに医療機関を受診しましょう。
(※1 参考)日本循環器学会|2025年改訂版 心不全診療ガイドライン
ストレスや精神的要素
強い不安やストレスは夜間の呼吸の乱れを引き起こすことがあり、特に寝る前や中途覚醒時に症状が現れやすいです。
精神的な緊張が交感神経を刺激すると、呼吸が浅く速くなり、動悸や発汗を伴うこともあります。
一過性の息苦しさであっても、場合によってはパニック発作へと発展することもあります。
睡眠時の息苦しさに精神的要因が関与している場合、日中のイライラや気分の落ち込みを伴うケースが少なくありません(※1)。
持続的な精神的負担は睡眠の質を下げ、症状の悪循環を招くため、必要に応じて専門的なカウンセリングや心療内科・精神科の受診を検討しましょう。
(※1 参考)日本不安症学会 / 日本神経精神薬理学会|パニック症の診療ガイドライン
睡眠中の呼吸困難は一瞬だけなら大丈夫?注意すべき症状と受診の目安
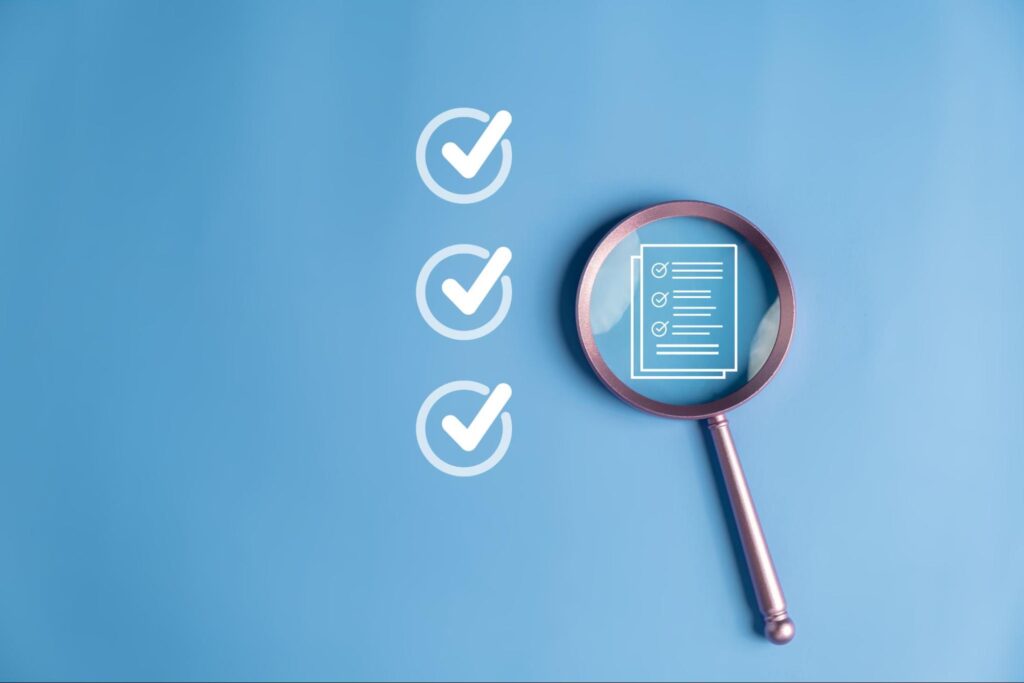
睡眠中の呼吸の乱れは、一瞬(数秒程度)であれば健康な人でも見られる生理現象で、すぐに深刻な問題になることはほとんどありません。
しかし、一瞬の呼吸困難であっても頻繁に繰り返され、他の症状を伴う場合は注意が必要です。
以下に、睡眠時の呼吸困難で疑われる主な原因別の受診目安をまとめています。
| 疑われる原因 | 受診が推奨される症状例 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | ・寝ている間の呼吸停止(自覚・指摘)・大きないびき・朝の強い眠気やだる |
| 呼吸器の病気 | ・夜間の持続的な息苦しさ・呼吸音の異常(ゼーゼー、ヒューヒュー)・夜間や早朝の咳 |
| 心臓や血管の病気 | ・夜間や明け方に突然の息切れや動悸・胸の圧迫感・足や顔のむくみ |
| ストレスや精神的要素 | ・睡眠中や入眠時の息苦しさの頻発・動悸、発汗、強い不安感・日中のイライラや落ち着かないなどの精神症状 |
睡眠中の呼吸困難の原因はさまざまで、自己判断で異常の有無を見極めるのは困難です。
無呼吸の頻度や程度にかかわらず、一瞬の呼吸困難でも強い恐怖を感じる場合は一度医療機関に相談してみましょう。
夜中の急な息苦しさへの対策・セルフケア方法

睡眠中の急な息苦しさは、以下のセルフケアで改善する場合もあります。
- 寝姿勢改善:横向き寝、枕の高さ調整
- 鼻づまり対策:鼻うがい、加湿
- ストレス対策:深呼吸、入浴習慣
- 生活習慣改善:適度な運動、禁煙・禁酒
それぞれの対策について詳しく解説していきます。セルフケアのみで改善が難しい場合や症状が重い場合は、早めに医療機関へ相談することも大切です。
寝姿勢改善:横向き寝、枕の高さ調整

睡眠時の息苦しさ対策として「横向き寝」と「枕の高さ調整」が有効です。
仰向けで眠ると、重力の影響で舌や軟口蓋が気道を塞ぎやすく、一時的な無呼吸や息苦しさを引き起こす場合があります。
横向きで寝ることで、気道の閉塞が減り、呼吸困難やいびきの軽減が期待できます。
また、睡眠時の気道確保には枕の高さも重要で、首と背骨が自然に一直線になる高さが理想とされています。
実際に、睡眠時無呼吸症候群の軽症例では、体位調整が非薬物療法として用いられ、睡眠の質や酸素供給の改善に寄与することが報告されています(※1)。
(※1 参考)日本呼吸器学会|睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020
鼻づまり対策:鼻うがい、加湿

鼻づまりは睡眠時の呼吸困難や無呼吸症状を悪化させるため、鼻腔を清潔に保ち、粘膜の炎症を抑えることが重要です。
以下は代表的なセルフケア方法です(※1)。
- 鼻うがい(鼻洗浄):生理食塩水で粘膜の花粉・ホコリを洗浄
- 加湿:室内湿度50〜60%で粘膜の乾燥防止
- 鼻を温める:蒸しタオルや入浴で鼻粘膜のうっ血を改善
これらのセルフケアの主な目的は、鼻粘膜保湿、アレルゲン・粘液・雑菌除去で、耳鼻咽喉科でも推奨される実用的な方法です。
物理的に鼻腔を広げる鼻腔拡張テープは根本治療ではないものの、就寝時の一時的な効果が期待でき、セルフケアとして役立つと考えられています。
症状が長引いたり他の症状(発熱、激しい痛み)がある場合は、耳鼻咽喉科の受診が必要です。
(※1 参考)日本鼻科学会|鼻副鼻腔炎診療の手引き
ストレス対策:深呼吸、入浴習慣
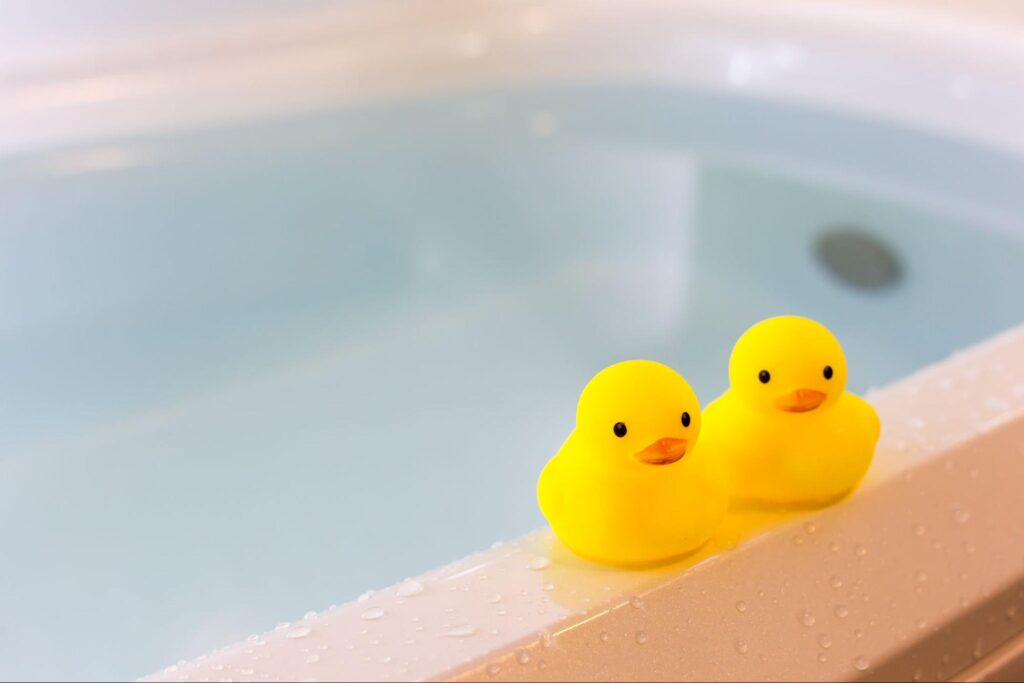
精神的ストレスや不安は交感神経を刺激し、睡眠中の息苦しさや無呼吸発作を誘発することがあります。
心身の緊張を和らげて安眠を促すには、副交感神経を優位にする「深呼吸」と「入浴」が有効です(※1)。
ゆっくり深く呼吸することで心拍や呼吸リズムが整い、短時間でもネガティブな感情を軽減しリラックス効果を高めます。
入浴は身体を温めて血流を促進し、温熱・浮力・水圧作用によって副交感神経を優位に導きます。
深呼吸と入浴は手軽に取り入れやすく、自律神経のバランス調整や睡眠の質向上を目指す習慣として推奨されます。
(※1 参考)株式会社バスクリン|入浴-健康増進
生活習慣改善:適度な運動、禁煙・禁酒

睡眠時無呼吸症候群の治療では、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせた運動療法が推奨されています(※1)。
運動による体重減少がなくても、レジスタンス運動により呼吸筋が鍛えられ、無呼吸症状の改善に効果が期待できます。
喫煙や飲酒は気道の炎症や筋肉の弛緩を招き、睡眠時の無呼吸や低呼吸を悪化させる要因です。
運動、禁煙、禁酒(または節酒)は、呼吸状態の改善だけでなく、全身の健康維持や他の治療効果を高めるための重要な基盤となります。
(※1 参考)日本呼吸器学会|睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020
「睡眠中の息苦しさ」以外の症状に応じた受診先の選び方

睡眠中の呼吸困難に付随する症状で受診先を選ぶことで、スムーズな治療につながりやすくなります。
- いびき、日中の眠気、喘鳴:呼吸器内科
- 鼻づまりや扁桃肥大など上気道の異常:耳鼻咽喉科
- 動悸、胸の圧迫感、手足のむくみ:循環器内科
- 激しい不安、恐怖、気分の落ち込み:心療内科
睡眠中の息苦しさに関連する症状と、それぞれの診療科について詳しく解説していきます。
受診先に迷う場合、まずかかりつけ医に相談し、症状や既往歴に応じて適切な診療科への紹介を受けると安心です。
いびき、日中の眠気、喘鳴:呼吸器内科

睡眠中の無呼吸に加え、いびき、日中の強い眠気、咳、喘鳴がある場合、呼吸器内科の受診が推奨されます。
睡眠時無呼吸症候群は呼吸器内科が治療の中核を担い、呼吸機能や睡眠検査を通じて状態を評価します。
夜間や早朝の咳や喘鳴を伴う場合、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)など呼吸器疾患が背景にある可能性があります。
家族から無呼吸を頻繁に指摘される場合は、症状が進行している恐れがあるため、早期診断と治療介入が必要です。
鼻づまりや扁桃肥大など上気道の異常:耳鼻咽喉科

鼻通りの悪さ、扁桃肥大、アデノイド肥大など、上気道に問題がある場合は耳鼻咽喉科の受診が推奨されます。
睡眠中の呼吸障害は鼻腔や咽頭の問題が原因となることも多く、耳鼻咽喉科による専門的な評価が必要です。
必要に応じて外科的処置が行われるケースもあり、気道閉塞の根本的な改善が期待できます。
鼻腔炎症や形態異常の治療は呼吸確保と酸素供給の改善に直結します。鼻や喉で気になる症状があれば早めの受診を検討しましょう。
動悸、胸の圧迫感、手足のむくみ:循環器内科

夜間の息苦しさに加え、動悸、胸の圧迫感、むくみがある場合は、心不全や不整脈などの循環器疾患が疑われます。
睡眠中の低酸素状態は心臓や脳への負担を増加させ、心血管疾患や脳血管障害の発症や再発リスクを高めるため注意が必要です。
循環器内科では既往症や合併症リスクを総合的に管理し、必要に応じて他科と連携した包括的な治療が行われます。
心臓や脳の病気は命に関わる深刻なリスクがあるため、自覚症状があれば速やかに循環器内科での精密検査を受けることが推奨されます。
激しい不安、恐怖、気分の落ち込み:心療内科

睡眠中や入眠時の強い不安感、動悸、発汗、恐怖感が繰り返し現れる場合は、心療内科での相談が適切でしょう。
背景にパニック発作、不安障害、うつ状態があると、呼吸困難や睡眠障害を引き起こすこともあります。
突然の恐怖感に加え、日中の気分の落ち込みや集中力低下が見られるケースでは、生活への影響が大きくなります。
心療内科では専門的カウンセリングや薬物療法を組み合わせ、症状の改善と再発予防を図ります。
精神症状が中心の場合は精神科が適応ですが、受診先に迷う時は心療内科やかかりつけ医に相談し、適切な紹介を受けると安心です。
よくある質問

睡眠時に急に息が苦しくなる症状について、よくある質問をまとめました。
Q.睡眠時無呼吸症候群で死亡することはありますか?
重症の睡眠時無呼吸症候群は、心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患リスクを大きく高め、突然死につながる可能性があります。
症状に気づいた段階で、早めに医療機関で検査を受けることが大切です。
Q.睡眠中に急に息が吸えなくなるのが一瞬だけでも病気の疑いがありますか?
数秒程度の無呼吸でも繰り返し起こる場合は、睡眠時無呼吸症候群や他の疾患の可能性があります。
頻度が高く、いびきや日中の眠気など他の症状を伴う場合は、医療機関の受診を検討してください。
Q.どんないびきだと病気が疑われますか?
いびきが途中で止まり、しばらくして大きないびきとともに呼吸が再開するパターンを繰り返す場合は、睡眠時無呼吸症候群が疑われます。
睡眠中に十分な酸素が取り込めていないサインであり、放置すると重篤な合併症リスクが高まるため、早めの受診が推奨されます。
まとめ

睡眠中や入眠時の急な息苦しさが繰り返し起こる場合、睡眠時無呼吸症候群、呼吸器疾患、循環器疾患、精神的要因などの関与が考えられます。
夜間の低酸素状態を放置すると、高血圧、心不全、脳卒中などの深刻な健康リスクが高まります。
本記事を参考に、無呼吸に伴う症状にも注意して早めに医療機関で検査を受けましょう。
当院では脳神経外科の視点から、将来の脳血管疾患予防も見据えた治療を行っています。
睡眠時無呼吸症候群には、CPAP治療のほか、併設歯科との連携によるマウスピース治療にも対応可能です。
睡眠時の呼吸困難、日中の強い眠気、起床時の頭痛などでお悩みの方は、当院へご相談ください。スムーズにご案内できるネット予約もご利用いただけます。





