
おひさまノート
CPAP治療の保険適用条件と費用|自費購入・生命保険の給付金・オンライン診療まで解説
目次
CPAP治療は、睡眠中の無呼吸が持続する限り基本的に継続が推奨されます。
治療期間が長期に及ぶため、健康保険の適用可否は費用負担に関わる重要なポイントです。
結論として、保険診療でCPAP治療を受けるには、中等症以上の睡眠時無呼吸症候群の診断が前提条件となります。
この記事では、CPAP治療の保険適用条件や月々の費用目安、自費購入の費用、民間保険の入院給付金まで詳しく解説します。
CPAP(シーパップ)は睡眠時無呼吸症候群の治療に使用する装置

CPAP(シーパップ:持続陽圧呼吸療法)治療は、睡眠中に鼻にマスクを装着し、一定の圧力で空気を送り込むことで気道の閉塞を防ぐ治療法です。
CPAP装置は、装置本体・エアチューブ・専用マスクの3つの主要部品から構成されます。
睡眠時無呼吸症候群の標準的治療として世界的に広く行われており、中等症以上の症例に有効とされています。
毎晩継続することで、睡眠の質の改善や重篤な合併症リスクの低減に期待できます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査方法と費用目安

睡眠時無呼吸症候群の検査は段階的に進められ、問診や簡易検査の結果に応じて精密検査の内容が選択されます(※1)。
| 検査の段階 | 内容 | 費用目安(3割負担の場合) |
| 1.初診時(外来) | 問診・血液検査・質問票などの基本的なスクリーニング検査。 | 約3,000~5,000円 |
| 2. 簡易検査(自宅) | 自宅で簡易モニター機器を装着し、睡眠時の呼吸状態・酸素飽和度・心拍数などを記録。 | 約3,000円前後 |
| 3. 精密検査(入院) | 必要に応じて1〜2泊の入院で、脳波・心電図・呼吸パターンなどを詳細に測定。 | 約20,000円〜50,000円 |
精密検査は、簡易検査で診断がつかない場合や、重症度・合併症の精査が必要なケースなど、医師の判断により実施されます。
睡眠時無呼吸症候群の診断・治療に必要な検査のため、健康保険が適用となる場合がほとんどです。
CPAP治療の健康保険適用(公的医療保険)について
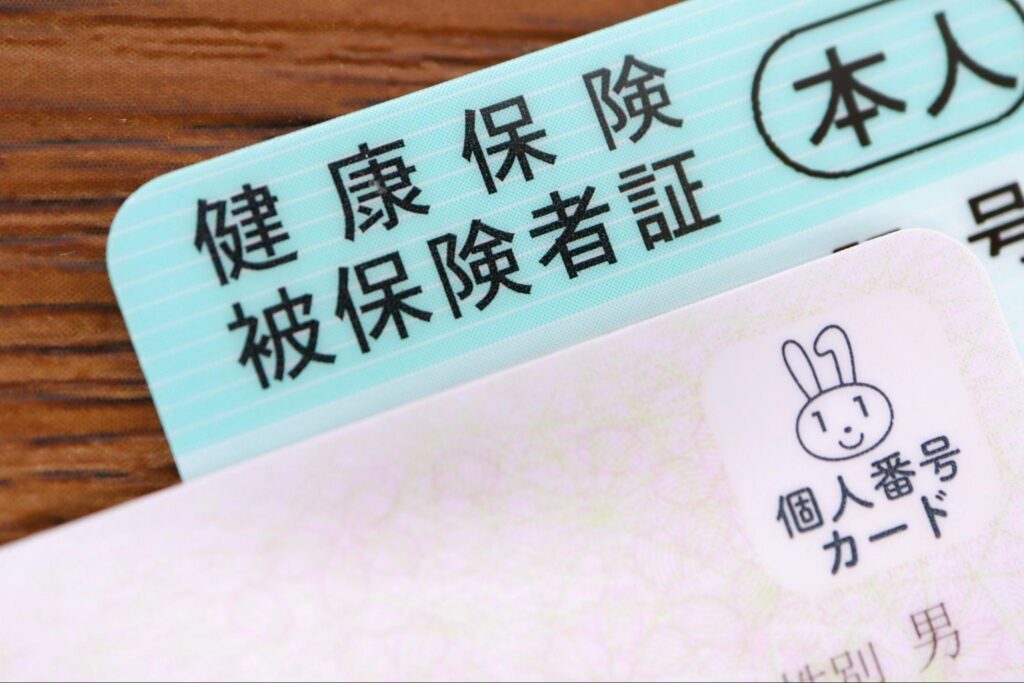
保険診療でCPAP治療を受けるためには、一定の基準や条件を満たす必要があります。
ここでは、CPAP治療で健康保険が適用される条件と、自費診療となるケースについて解説します。
- 保険診療でCPAP治療を受けるための基準・条件
- 健康保険が適用されない(自費診療)のケース
保険診療でCPAP治療を受けるための基準・条件

CPAP治療に健康保険が適用されるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 中等症以上の睡眠時無呼吸症候群の診断を受ける
- 医師が治療の必要性を判断する
- 原則月1回以上の診察を受ける
- CPAP使用率は1日4時間以上かつ月70%以上を維持
保険診療としてのCPAP導入は「精密検査でAHI20以上」または「簡易検査でAHI40以上」の原則とされます。
症状や合併症が重い場合は、中等症以上の数値基準に満たなくても医師の判断でCPAP治療が適応されることがあります。
保険診療でCPAPを継続するには、原則として月1回以上の診察が必要です。
また、治療遵守の指標としてCPAP使用率が「1日4時間以上かつ月70%以上」に満たない場合は、保険適用が継続されない可能性があります。
健康保険が適用されない(自費診療)のケース

次の場合、CPAP療法は健康保険の対象外で全額自己負担となります。
- 軽症の睡眠時無呼吸症候群(例:AHIが20未満)
- 医師がCPAP治療の必要性を認めていない
- 定期的な診察を受けられない
- 治療以外の用途や自己判断による使用
CPAP治療が保険診療として認められるのは、中等症以上の睡眠時無呼吸症候群、または医師が必要と判断した場合に限られます。
単に「いびきの音が気になる」「体調を整えたい」など、治療以外の目的は健康保険の適用基準に該当しません。
定期診察や医師指示を逸脱した場合も、治療遵守ができないとして保険適用外となります。
訪日外国人や海外在住者など保険制度の枠組みから外れる方も、CPAP治療を含め保険診療の対象にはなりません。
CPAP治療にかかる費用|保険適用と自費購入の違い

CPAP治療の費用について、保険適用時と自費購入の2つに分けて解説します。
- 健康保険適用時の自己負担額(月額の目安)
- CPAP装置を自費購入する場合の費用
健康保険適用時の自己負担額(月額の目安)
睡眠時無呼吸症候群の診断後、CPAP治療を保険適用で受ける場合、3割負担で月額約5,000円が自己負担の目安となります。
費用には、CPAP装置のレンタル料と月1回の診察料が含まれます。
マスク、チューブ、フィルターなどの消耗品は、交換頻度や費用負担が医療機関ごとに異なるため事前に確認しておきましょう。
なお、初回は初診料や検査費用が加算されます。3割負担の目安は、簡易検査で約3,000〜5,000円、入院を伴う精密検査では約20,000〜50,000円です。
CPAP装置を自費購入する場合の費用
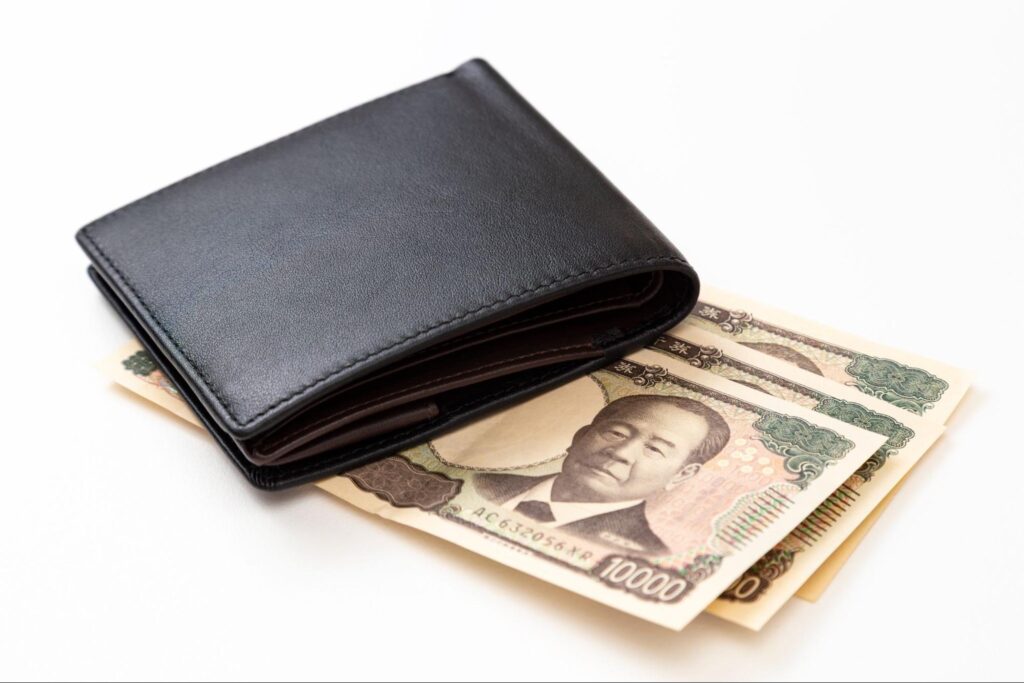
CPAP装置の本体価格の目安は15万〜40万円以上です。マスク、チューブ、フィルターなどの消耗品の交換費用も自己負担となります。
以下は、CPAP本体と主要な消耗品の価格帯と交換推奨期間の目安です。
| 項目 | 自費購入目安(税別) | 耐用期間・交換推奨期間 |
| CPAP装置本体 | 約15万円~40万円以上 | 5〜7年 |
| マスク | 約1万円~3万円 | 1年に1回以上 |
| チューブ | 約数千円~1万円 | 1年に1回以上 |
| フィルター | 約数百円~数千円 | 3〜6ヶ月 |
近年、CPAP装置本体の耐久性は向上しており、長期使用できれば保険診療よりコストを抑えられる可能性があります。
一方、保証期間は通常1〜2年であり、期間終了後の機器トラブルは自己負担となるため注意が必要です。
CPAP治療のオンライン診療について

2024年6月の診療報酬改定以降、CPAP治療をオンライン診療で継続できる医療機関が増えています。
ここでは、CPAP治療におけるオンライン診療に関するポイントを解説します。
- オンライン診療でも健康保険が適用される
- 初診からのオンライン診療は条件付きで可能
- オンライン診療はシステム利用料がかかることも
オンライン診療でも健康保険が適用される
2024年6月の診療報酬改定により、CPAP治療のオンライン診療は正式に健康保険の対象となりました。
2020年〜2022年の新型コロナ禍でオンライン診療が広く認められ、CPAP治療にも実質的に活用されてきました。
その後、2022年の診療報酬改定で制限緩和がさらに進み、2024年6月の改定で制度的に保険適用が明確化した流れです。
オンライン診療は臨時対応から制度化へと段階的に発展し、よりCPAP治療を続けやすい環境へ変化しています。
初診からのオンライン診療は条件付きで可能

原則として、初診からのオンライン診療はかかりつけ医が担当する場合に限られています。
既往歴、服薬歴、症状など医学的情報を十分に把握していることが前提となるからです。
ただし、必要な医学的情報が医師側で把握できれば、かかりつけ医以外でも対応可能とされています。
睡眠時無呼吸症候群に合併する疾患管理の必要性に応じて、対面診療を適宜組み合わせることも重要です。
(※1 参考)厚生労働省|オンライン診療の適切な実施に関する指針の概要
オンライン診療はシステム利用料がかかることも
オンライン診療におけるCPAP治療の診療報酬は、対面診療と大きな差はありませんが、やや低めに設定されています。
- 対面診療:250点
- オンライン診療:218点
※1
一方で、オンライン診療では診療報酬とは別にシステム利用料が発生する場合があります
金額は医療機関によって異なりますが、500円〜1,000円程度に設定されることが多いです。
加算によっては、オンライン診療が少し割高になる可能性があることに留意しておきましょう。
(※1 参考)厚生労働省|令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)
睡眠時無呼吸症候群と民間保険(生命保険・医療保険)について

睡眠時無呼吸症候群に関する民間保険の取り扱いについて、次の3つを解説します。
- 睡眠時無呼吸症候群の検査入院は給付金支払い対象になるか?
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)診断後の保険加入が難しい理由
- CPAP治療中でも入りやすい保険【引受基準緩和型】
「保障体制を整えたい」「万が一に備えたい」という方の参考になれば幸いです。
睡眠時無呼吸症候群の検査入院は給付金支払い対象になるか?

医師が入院を指示した場合、治療の一環として入院給付金の支払い対象となるケースが多いです。
基本的に、人間ドックや自発的な検査を目的とした入院は、入院給付金の対象にはなりません。
一般的に給付金を申請する際は、保険会社所定の診断書や証明書の提出が必要です。
なお、検査の結果、治療に該当しないと判断された場合や、治療が実施されなかったケースでは支払い対象外となることがあります。
詳しくは、加入する保険会社・共済などにお問い合わせください。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)診断後の保険加入が難しい理由

睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断された後は、医療保険や生命保険への加入が難しくなる場合があります。
睡眠時無呼吸症候群は慢性的な低酸素状態を引き起こし、脳卒中や心血管疾患などの重篤な合併症リスクを高めるからです。
保険会社は将来的な保険金支払いの可能性を慎重に審査するため、加入制限がかかることがあります。
CPAP治療を継続している方は、保険会社への事前告知義務にも注意が必要です。
CPAP治療中でも入りやすい保険【引受基準緩和型】
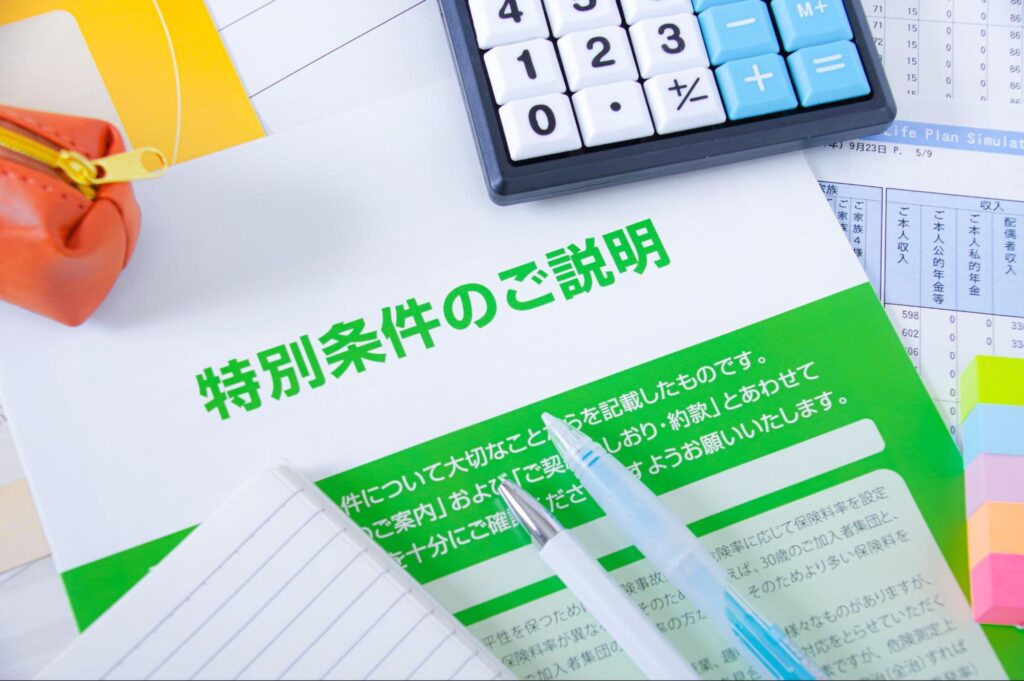
引受基準緩和型保険は、持病や既往症がある方でも加入しやすいよう告知項目を絞り、引受基準を緩やかに設定した保険商品です。
睡眠時無呼吸症候群でCPAP治療中の方でも、告知項目すべてに「いいえ」と答えられれば、原則として加入できます。
【引受基準緩和型の告知項目例】
- 最近3ヶ月以内に、医師から入院・手術・先進医療のいずれかをすすめられたことがありますか。
- 過去2年以内に、病気やケガで入院をした、または手術を受けたことがありますか。
- 過去5年以内に、ガン、上皮内ガン、肝硬変、統合失調症、認知症、アルコール依存症で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。
デメリットは、毎月の保険料が通常より割高になることが多いことです。
加入条件や告知内容は保険会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
よくある質問
CPAPの保険適用や自費購入について、よくある質問をまとめました。
Q.CPAPのレンタル料は医療機関によって変わりますか?
CPAPのレンタル料は診療報酬点数をもとに算出されるため、大幅な価格差はありません。
ただし、診療内容や消耗品の扱いで、若干の違いが生じることはあります。
Q.CPAP装置を自費購入したいのですが、どこで入手できますか?
CPAP装置を個人で所有する場合、メーカーから直接購入するか、医療機関や正規代理店を通じて入手するのが主な方法です。
なお、CPAPは高度管理医療機器のため、基本的に医師の診断や承諾なしに個人が購入することはできません。
薬と同じく、医師が必要と判断して処方した場合にのみ、CPAP装置の購入・使用が認められます。
Q.定期診察でCPAPのデータはどうやって確認するのですか?
CPAP装置の種類により、診察時のデータ確認方法は異なります。
メモリーカード内蔵機種の場合、診察日にメモリーカードを持参していただきます。
クラウド送信対応機種では、カードを持参せずにデータ確認が可能です。
まとめ
CPAP治療は、一定の条件を満たせば健康保険が適用され、費用負担を抑えて治療を継続することが可能です。
保険診療における月額費用の目安は3割負担で約5,000円で、装置のレンタル料と診察料が含まれます。
CPAP装置を自費購入する場合、長期的使用で費用を抑えられる可能性がありますが、故障や消耗品費用は自己負担となります。
当院では睡眠時無呼吸症候群の検査・治療を行っています。
現在のところオンライン診療には対応しておりません。今後、検討していく予定です。
CPAP治療に加え、併設する歯科との連携でマウスピース治療にも対応可能です。
いびき、日中の強い眠気、起床時の頭痛などでお悩みの方は、当院へご相談ください。スムーズにご案内できるネット予約もご利用いただけます。





