
医療コラム
緊張型頭痛について知ろう!
目次
頭痛は多くの人が1度は体験したことのある症状です。
頭痛には多くの種類があり、緊張型頭痛をお持ちの患者さまは
日本でも20~30%といわれています。
みなさんがよく耳にする片頭痛と比べても明らかに多いことがわかっています。
今回は緊張型頭痛について日本脳神経外科学会専門医の院長が解説をします。
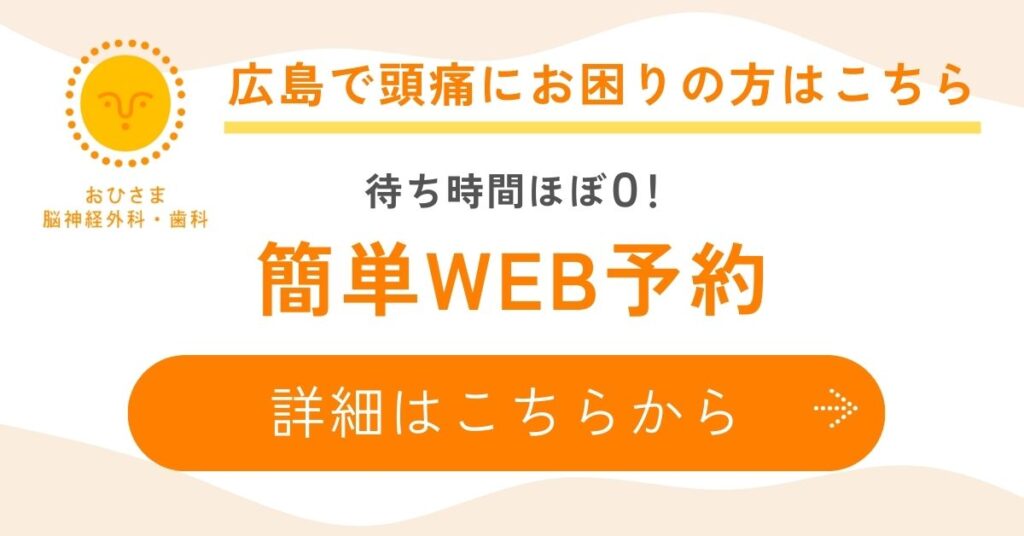
緊張型頭痛とは?

軽いものから中等度の痛みで、頭全体か後頭部に鈍い締め付け感、
圧迫感のある頭痛が出現します。
患者さんによっては、「ベルトやはちまきで頭が締め付けられている」と訴える人もいます。
頭痛は一次性頭痛(原発性頭痛)と二次性頭痛に大きく分けられます。
二次性頭痛は、他の病気が原因となっており、「脳」「眼」「鼻」「のど」
「歯」「首」とこれ以外にもさまざまな病気が関わっています。
特に髄膜炎や脳腫瘍、脳出血など脳に影響を及ぼすものには注意が必要です。
これに対し一次性頭痛は、他の病気が要因ではありませんが、
頭痛発作をくり返したり持続することが問題となります。
緊張型頭痛も一次性頭痛の1つで、一次性頭痛には
ほかに片頭痛と群発頭痛が主なものです。
緊張型頭痛は、一次性頭痛のなかで最も多い頭痛で、世界人口での
有病率は38%といわれています。
参考文献:一般社団法人-日本頭痛学会HP
https://www.jhsnet.net/ippan_zutu_kaisetu_03.html(参照2024-12-12)
緊張型頭痛の原因
緊張型頭痛の発生機序に関してはいまだに不明な部分も多いですが、
末梢性感作が関わっているとされます。
頭頸部筋群の緊張が強くなることで、サブスタンスP・グルタミン酸などの
神経伝達物質が放出され、それらが刺激となって痛み物質が増えていきます。
すると、筋肉・筋膜・皮下組織などが痛み刺激に敏感になってしまいます。
「ストレートネック」「VDT症候群」「疼痛閾値」などが
緊張型頭痛を誘発させる原因になっているとも考えられています。
それぞれ簡単に説明していきましょう!
ストレートネック
緊張型頭痛に関係するのが、頭頸部筋群というものです。
簡単にいうと、首の付け根から頭部にかけての筋肉群です。
さまざまな筋肉をまとめて頭頚部筋群と称してしますが、
その中でも「僧帽筋」と「前頭筋」は
緊張型頭痛と特に関連が深いとされています。
頭頚部筋群の緊張を亢進させる原因の一つとして、
ストレートネックがあげられます。
前かがみになった重い頭を支えるために後頭部の筋肉(とくに僧帽筋)が緊張し、
頭痛を生じる要因となります。
※僧帽筋:首の付け根から肩や背中の上部にかけてつながる筋肉
※前頭筋:顔の表情を作る筋肉の一部で、おでこの正面部分の筋肉
VDT症候群(Visual Display Terminal症候群)
最近では、VDT症候群の関与も頻度が高いです。
VDT症候群は、コンピューター機器を使用する仕事についている
人に多く認められるものです。
同じ姿勢でPC・タブレット・スマホなどの液晶画面を見る作業や週間が
日々続くことで頭・首の筋肉の緊張を亢進させ、
緊張型頭痛を引き起こす環境を生み出しているといえます。
疼痛閾値
緊張型頭痛は、頭蓋を取り巻く筋肉が持続的に収縮しておこる頭痛です。
筋肉の血の流れが悪くなり、老廃物がたまると、疼痛刺激が
長引いて痛みを感じる閾値(いきち)が正常より低く
なることで頭痛を引き起こす可能性があると言われています。
その他
歯の問題であったり、睡眠不足や不規則な食生活などの生活習慣などが考えられます。
その他にも、うつやストレスなどの心理的な要因などもあるでしょう。
ストレスによって神経や筋肉が過度に緊張し、
筋肉に疲労物質がたまったり、脳内の痛みの調整機能が
うまく働かなくなったりして頭痛が起こります。
参考文献:日本頭痛学会誌 シンポジウム9-4【緊張型頭痛の発症メカニズム】
50巻(2023)pp,103-105https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjho/50/1/50_103/_article/-char/ja
緊張型頭痛の症状

- 頭をベルトで締め付けられるような痛みや重苦しさ
- 頭の両側に痛みを生じる
- 鈍い痛みが特徴だが、寝込んだりするほどの痛みではない
- 首や肩のこりを伴うことが多い
緊張型頭痛の診断基準
以下に緊張型頭痛の診断基準の一部を示します。
頭痛の月あたりの回数・頻度でも分類されます。
【緊張型頭痛の診断基準】(抜粋)
・頭痛は30分~7日間持続する
・頭痛は以下の特徴の少なくとも2項目を満たす
1.両側性
2.性状は圧迫感または締め付け感(非拍動性)
3.強さは軽度~中等度
4.歩行や階段の昇降のような日常的な動作により憎悪しない
・以下の両方を満たす
1.悪心や嘔吐はない
2.光過敏や音過敏はあってもどちらか一方のみ
・他に最適な診断がない
緊張型頭痛の診断はセルフチェックも重要になります。
そのため、受診の前に「頭痛がどれくらい続いたか」
「何をすれば頭痛が緩和したか」「頭痛以外の症状はあったか」
などをメモしておくと診察の助けになります。
参考文献:国際頭痛分類第3版(ICDH-3)日本語版
緊張型頭痛の治療

1.緊張型頭痛の急性期治療
急性期治療は頓挫薬による薬物療法が中心となります。
緊張型頭痛の痛みは軽度のものが多く、
鎮痛薬を必要としない場合も多いです。
しかし、患者さんは不安感などにより服用してしまうことがあるため、
痛みが中等度以上の場合など、本当に必要な場合のみ服用することや
頭痛ダイアリーを記載して1ヶ月の服薬回数を把握することなどが
大切です。
これは薬の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛:MOH)を
予防するためでもあります。
患者さんにもご自身の頭痛に関して理解をしてもらうことが重要になりますね。
2.緊張型頭痛の予防療法(薬物療法)
予防療法は頻度が高い頻発反復性緊張型頭痛や慢性緊張型頭痛が適応となります。
緊張型頭痛は実際の症例でも、うつや不安を合併している場合も多く、
予防療法の中心は抗うつ薬による内服療法を行うことがあります。
特に抗うつ薬であるアミトリプチリン(トリプタノール)が
予防効果が高い薬剤として使用されています。
アミトリプチリンをまずは、少量から始めます。
増量も可能ではありますが、口喝や便秘、眠気などの副作用が
出現することもあり、少量での使用が望ましいとされています。
予防薬はあらかじめ長期に服用する必要があります。
治療の効果に関しては、最低でも3ヶ月を目安に判断し、
増量等をしても効果が得られない場合は、
他の薬に変更したり、追加をしたりなどをしていきます。
3.緊張型頭痛の予防療法(非薬物療法)
非薬物療法では、薬物を用いず、精神療法および行動療法、
リラクゼーション法、運動療法、理学療法、鍼灸などによって
緊張型頭痛を改善していきます。
非薬物療法は、すべての緊張型頭痛患者さんに考慮されるべき
治療であるといわれています。
精神療法および行動療法
頭痛ガイドラインで効果があるとされているのが、
精神療法および行動療法です。
精神療法および行動療法である筋電図バイオフィードバック療法、
認知行動療法、リラクゼーション法などがあります。
緊張型頭痛は、精神的ストレスが原因で起こることが多いため
精神療法が有効です。
ストレスなどの精神的なことが原因で頭痛が起こる方は、
普段と気分を変えて、マッサージやヨガに行くのもいいかもしれません。
湯船に浸かるときには、アロマを使用したりと
ご自身に合ったストレス解消法を見つけましょう!
理学療法(運動療法)
理学療法には、運動やマッサージ、姿勢の矯正などがあります。
頭や肩の筋肉をほぐすためには、適度な運動やストレッチが効果的です。
特に、「肩こり体操」や「頭痛体操」はすぐにでもできる
予防法なのでおすすめです。
猫背姿勢は首や肩の筋肉を張らせるため、
意識して背筋をまっすぐにしたり、肩が丸まらないように
気をつけるのも大切です。
他にも、温熱療法といって首の後ろや背中を温めることで、
筋肉の緊張を緩めて血流を促すことが期待されます。
首や肩の張り強い場合は、湯船に浸かるといいでしょう。
鍼灸
鍼灸とは、鍼(はり)と灸(きゅう)を用いて
身体の「ツボ」に刺激を与えることで、不調の改善や予防を
行う伝統的な東洋医学です。
・鍼は、細くて丈夫な針を身体の特定の点に刺して筋肉の
緊張をほぐしたり、血行を改善したりします。
注射針とは異なり、成人の毛髪くらいの細さで、
先端は特殊な角度になっているため刺しても痛くありません。
・灸は、ヨモギを乾燥させて細かくしたもぐさを
皮膚の上に置いて焼き、身体内部を温めて自然治癒力を高めます。
鍼灸には、筋肉の緊張を緩和する、血行を促進する、
ストレスを軽減する、自律神経を調整する、自然治癒力を
高めるなど様々な効果があります。
緊張型頭痛でお困りのみなさんへ

緊張型頭痛は幅広い年齢層で経験する、一番多い一次性頭痛です。
頭痛は起きるけど、病院に行くほどではないなと、
感じている方も多いのではないでしょうか。
忙しい働き世代の方々、育児中のお母さまなど
お時間に余裕がない方は、先程もお話したように
家でできる予防法や改善法も多くございます。
また、当院では保育士が在籍しており、無料でお子様をお預かりしていますので、
子育て中のママ・パパにも、安心して受診していただけます。
ですので、まずはおひさま脳神経外科・歯科を受診してみてください。
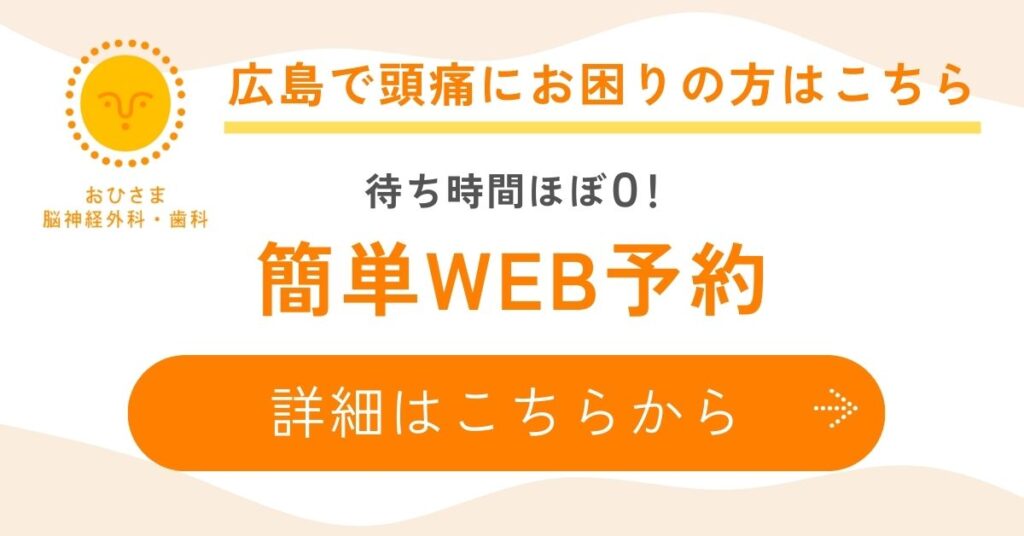
当院は、日本脳神経外科学会専門医が診察を診察しており、
非常勤で漢方薬治療を専門としている
日本東洋医学会専門医・日本内科学会認定医が診療しています。
おひさま脳神経外科・歯科
当院は、待ち時間短縮のため完全予約制となっています。
当日でもご予約受付します。
はじめて当院を受診される方はWeb予約をお願いします。
・脳神経外科Web予約はこちらから
以前受診したことがある方は、お電話またはデジスマにてご予約ください。
・脳神経外科082-569-5728
・脳神経外科のデジスマはこちら
・漢方内科のデジスマはこちら





